―― 始まりを告げる音が内から鳴り出す。
けれど、その音の始まるきっかけは誰も知らない。
「ねぇ、邪見さま。殺生丸さまにはいつ会っていいの?」
「…まーたそれか、りん」
西国に戻って半月余り、改めて“当主”として着任した殺生丸は当然の事ながらその執務に追われていた。
帰還した当初こそ、祭騒ぎのように城の者たちに迎え入れられ、歓喜と嘆きの声が暫くは収まらなかったのはまだ記憶に新しい。
半月もあっという間に過ぎ去り、いよいよ落ち着いてくるかと淡い期待を抱いていたものの、虚しくもそれは叶わなかった。
来る日も来る日も朝日が昇る前から殺生丸は書斎に篭り、また夜が深くなるまでその姿を見ることは無い。
―― 殺生丸さまのお顔を見たのはいつかなぁ…。
りんがそんなことを思うのも日増しに多くなるばかりで…。
ついに始まったのが「いつ会えるの?」という問い出しだった。
始まったばかりの頃は邪見も侍女たちも口を揃えて「もう少ししたら…」となんとか回避していたものの、流石に何度も効きはしない。
「邪見さま!」
「しつこいぞ、りんっ!!殺生丸さまはお忙しいのじゃ!!」
「それは…、分かってるけど…」
しょんぼりとするりんの気持ちが分からなくも無い邪見にとって、この繰り返しは聊か辛くもあった。
本当に連れて来て良かったのか、はたまた悪かったのか…。
少し不憫に思っていると、ふと、少女の視線が自分の手元に移ったのが分かった。
その途端、大きな漆黒の瞳は期待いっぱいに輝く。
「邪見さま、それどこに持っていくの?」
瞳の輝きに気付いた時に逃げるべきだったと邪見は後悔した。
実を言えば、邪見は湯浴みから戻った殺生丸に着替えを持っていく途中であったのだ。
「べ、別にこれは殺生丸さまの御召替えなどではないぞっ!?」
「殺生丸さまのお着替えなんだね。じゃあ、私が持って行く!」
―― わしってバカー!!
「持って行くだけだもん。いいでしょ?邪見さま」
期待が込められた輝く瞳に否と言える訳がなかった。
渋々りんに着替えを手渡す。
「良いか、りん。襖の所に置いて来るだけでいいんじゃぞ?置いたら直ぐに戻って来い、良いな?」
「うん、分かった!私に任せといて」
大事に着替えを抱え、りんは邪見の元を後にした。
もしかしたら殺生丸に会えるかもしれないという期待を抱きながら。
廊下を暫く進むと見慣れた部屋が見えてきた。
忙しくなる以前は暇さえあれば会う為に毎日の様に通った部屋。
暫く訪れなかったせいか、なんだか懐かしい気もした。
―― 殺生丸さま、いらっしゃるかな…?
ポツリとそんなことを思いながら、りんは静かに部屋の襖を開けた。
それと同時に僅かな冷気が流れ出てきたのは気のせいだろうか…。
室内は薄暗く、人っ子一人の気配すら感じられなかった。
「…誰もいないのかな?」
言われた通りに入り口付近に着替えを置き、早々に立ち去ろうとしたが、何となくりんは足を止めた。
今居るのは書斎と繋がっている空き部屋。
誰が使うわけでもなく、こことは別に勿論きちんと書斎への入り口はあるのだが、何故か通路代わりに使われていた。
それでも部屋が余っているほどで、改めてこの城の広さをりんは実感した。
そして、もしかしたら奥に妖がいるのではないかと、そう少女は思ったのだ。
無意識に抜き足差し足で室内を進んでゆく。
もう少しで書斎に辿り着く所まで行ったところで、奥からカタンッと物音が聞こえた。
その瞬間、りんは確信する。
―― 殺生丸さまがいる!!
躊躇うことなくりんは思い切り目の前の襖を開け放った。
「殺生丸さま…!!」
溢れ出す嬉しさを抑えきれず、少女は妖の名を叫ぶ。
それとほぼ同時に振り向いた黄金色の双眼は、驚いたように少し見開かれていた。
「せっ…」
そんな殺生丸の様子を可笑しく思いながらも、やはり会えた嬉しさの方が勝るもので、すぐさま駆け寄ろうとしたが、ピタリと少女は足を止めた。
何故、止まったのか自分自身でも分からない。
ただ分かるのは目の前にいる妖が上半身裸だったという事だけ。
たったそれだけの状況に自分の頬が急激に蒸気してゆくのを感じた。
改めて見る逞しい腕、流れるように美しい白銀の髪の間から覗く大きな背中、そして厚い胸板。
かつてあの腕に抱きかかえられながら生を再び受けた幼き頃の記憶が一気に脳内を駆け巡った。
何故この状況でそんな昔のことを思い出したのか。何故こんなにも頬が熱いのか。
いきなり胸が締め付けられるように苦しい。
「せっ、しょう…丸さ、ま…」
切なそうな声で名を紡ぎながらりんはその場に倒れ込む。
間一髪で崩れ落ちる小さな体を受け止めながら殺生丸は何とも言えない面持ちだった。
「…邪見さま、私…病気かもしれない」
倒れた後、目を覚ますと見慣れた天井が目に入り、ここは自室であると直ぐに分かった。
隣でせっせと看病をする邪見にりんはポツリを呟く。
「なっ…、病気じゃと!?ま、まさか…りん、殺生丸さまに何か…!!」
「私ね、殺生丸さまに会ったの」
―― やっぱり…!!
「それで急に胸が苦しくなって、あっつくなって……倒れちゃった。ごめんね、邪見さま」
良からぬ想像しか出来ていない邪見を尻目に、りんは皆に迷惑を掛けてしまった申し訳無さと自分の情けなさを謝った。
しかしながら、そんな言葉は邪見には届かず…。
「良いか、りん!いくらお相手が殺生丸さまだからと言って臆することはっ…!!」
「落ち着きなさいませ、邪見殿」
慌てふためきながら意味の分からないことを口走る邪見をいつの間にか襖の開けて入って来ていた女中頭が咎めた。
「妙なことを口走るものではありませんよ」
「し、しかしじゃなっ…!!」
「それはまだ先のお話ですよ。ささ、私はりん様と二人でお話したいので席をお外しくださいな」
有無を言わせない無言の威圧に邪見は部屋から放り出されてしまった。
先程の女中頭の口調からして、自分が心配しているようなことは一切無いようではあるが、邪見にとってりんは孫のような存在。
なんとも複雑な心境であった。
「さて、りん様。ここからは女同士のお話ですよ」
「なになに?」
もったいぶるような女中の口調にりんはソワソワと急かすように話に乗った。
「先程の出来事ですが…あれは、病気でもあり決して本当の病気では御座いません」
「病気なのに病気じゃないの?」
「はい。何と申し上げれば宜しいのでしょうか…、りん様、ご当主に会えなくて寂しかったですか?」
「…うん、寂しかった」
「お会い出来た時、嬉しかったですか?」
「とっても嬉しかった!」
「その時、胸が苦しくなりましたか?」
「うん、なんでだろう…?」
確認を込めた最後の問い掛けの後、一人うなだれてしまった少女の様子を見て、思わず噴き出しそうになった。
それは決して蔑みではなく、その愛おしさからだ。
質問のひとつひとつにクルクルと表情は変わる。なんと可愛らしいことか。
「りん様、」
少し咳払いをして姿勢を正す。
「実は私も同じ経験があります」
「えっ、殺生丸さまに!?」
「いえいえ、ずっと…ずーっと昔の話で御座いますよ。私もりん様と同じ病気になりました。
なんと言う名前かりん様は存じませんか?」
「うん、分かんない」
キョトンと首を傾げる様を確認するかのように女中は一呼吸置くと、ゆっくりと口を開いた。
「それは、“恋の病”で御座います」
「こい…?」
傾がれた首を更に少し傾げる。
「お会いして嬉しいと思った、それと同時に胸が苦しくなった…それは恋で御座いますよ。
その殿方を好いておられるということで御座います」
「私が…?」
「ええ、」
「殺生丸さまを…、好き…?」
「きっと違いありません」
確信を促すように女中は頷くと、途端にりんは顔を真っ赤に染めてしまった。
自らの中に芽生えた感情に改めて気付いてみて戸惑う姿はきっと誰から見ても可愛らしいことだろう。
―― 若様も隅に置けない方…。
あわあわと慌てるりんを尻目に女中はコッソリとそんな事を思った。
しかしながら突然、目の前の少女から「あっ」と小さな悲鳴が上がる。
「で、でも、邪見さまの事もお城のみんなのことも好きだよ?」
その訴えのあまりの天然ぶりに可愛さ故の溜息しか出なかった。
もうそれは過去であれ、ここまで無垢な少女に常識があるようで無い世話焼きな従者、それに無口な妖の組み合わせの日々だったことを思うと女中は途方が暮れそうになった。
しかしながら、全部ひっくるめてそれは面白くもある。
「りん様、それは違います。邪見殿も含め、私共には胸が苦しくなったりされませんでしょう?」
「…うん、」
「それも“好き”には違いありませんが、“恋”とはまた別のもので御座いますよ」
「そっかぁ…。恋って苦しいんだ…」
「左様で御座いますね。しかし、幸せでもあります」
「どうして?」
「好いた方とお会い出来ますのは嬉しい事で御座いましょう?」
そう問い掛ける女中の微笑みの向こうには何かあたたかいものを感じた。
「うんッ」
今日も今日とて陽が沈み始めた頃、小さな足音は静かに襖の前でその音を止めた。
部屋の中に入ろうか否か迷い、しばしまた前でウロウロとする。
改めてまた立ち止まり、襖を開けようと一瞬は躊躇ったものの、意を決めて再び開けようと手を掛けると、自らが引く前に自動的に襖が開いた。
驚いて反射的に目を上げれば、そこには部屋の…もとい城の主が立っていた。
「…何をしている」
「せっ、殺生丸さま」
妖怪というのは人間よりも嗅覚が鋭いもので、ましてや犬の妖怪となれば尚のことである。
そのことを忘れていたのか否か、はたまた知らなかったのか、りんは「見つかってしまった!」という顔で冷や汗を流していた。
「あの、その…さっきはごめんなさい」
「…そう思うのなら大人しくしていろ」
呆れたように溜息混じりに言葉を吐いた妖を余所に少女は真剣な面持ちで顔を上げた。
「でもね、病気じゃなかったの!…あ、でも病気と言えば病気なんだけど…」
「………」
訳の分からないりんの言葉に殺生丸は怪訝な顔をするしかなかった。
何が言いたいというのだろうか。
しどろもどろになりながらも少女は懸命に何かを訴えようとしている。
一体、何を…。
「あのね、私…、」
ほんの数秒、僅かな沈黙が流れる。
「殺生丸さまのことが、好き」
一呼吸置いて、その言葉は小さくこの場の空間に響いた気がした。
目の前に佇む妖は僅かに目を見開いたままで何も言わない。
一世一代の大告白をした少女自身もう何が何やら、また倒れそうになったが、頬に触れてきた殺生丸の手にハッと我に返る。
「せっ、」
しかし名前を呼ぶことは叶わず、小さな唇は簡単に塞がれてしまった。
「んんっ……」
逃れようにも体は熱に侵され言うことを聞いてくれない。
ましてや後頭部はしっかりと固定されて…。
今までの分を含めたような、貪るような深い口付け。
「りん…、私を選んだのはお前だ。覚悟しておけ」
「はい、殺生丸さま」
頬を紅く染めたまま、りんは笑顔で答えた。
それを見つめながら、密かに殺生丸の瞳の奥が妖しく光っていたとは露知らず…。
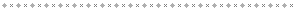
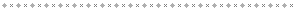
「空の模様」(現「世空色」) ハヤキ様宅にて、正式なキリ番じゃないにも拘わらず 『キリ番ニアピン賞』(笑) としてリクエストを受け付けてくださったので、有り難くも図々しくお願いして書いていただいた作品です。
そこで、絶対私が書けないようなテーマ 『恋の始まり、ピュアなりんちゃん』 をお願いしたところ、大輪の花を咲かせる手前の初々しい一瞬を、こんな素敵な文章で綴ってくださいました。……初恋っていいなあ……(笑)
ハヤキ様、ありがとうございました。
叙情的な殺りん小説満載のハヤキ様のサイトはこちらです。

